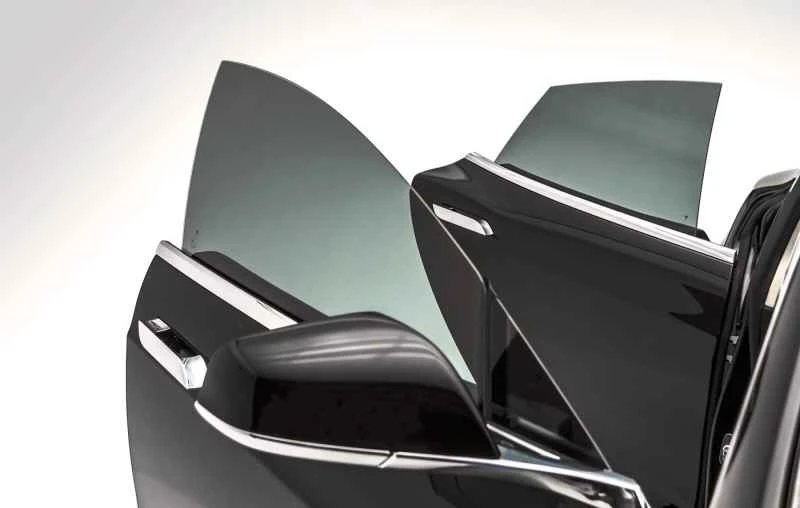Share this

2008年の米国サブプライム住宅ローン危機の翌年、ゼネラルモーターズ(GM)は破産を宣言しました。2013年には、世界的に有名なモーターシティ、デトロイトも破産しました。今日のアメリカの自動車産業はどのような状況にあるのでしょうか?
2026-03-01 07:13:23
·
·
#1

バッテリーがエンジンを始動できないからといって、必ずしもバッテリーの故障とは限りません。単に充電不足が原因の場合もあります。エンジンを始動できるだけの十分な充電量を維持している限り、バッテリーの充電量が40%でもまだ使用できます。バッテリー...